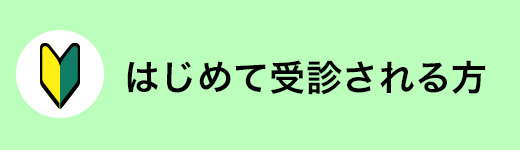肩関節痛
肩関節の痛みは多くの疾患が原因で起こります。代表的なものは、変形性肩関節症、腱板損傷、凍結肩、石灰沈着性腱板炎、肩関節脱臼、肩関節唇損傷、上腕に当筋腱断裂、上腕骨骨折、肩甲骨骨折などが挙げられます。
ここでは肩関節痛があるときによく使われる「五十肩(肩関節周囲炎)」について少し触れていきます。
「五十肩」「肩関節周囲炎」ってなに?
五十肩とは肩の痛みやそれによって肩の運動制限がある状態のことです。最近では肩関節周囲炎ともいわれています。肩が痛くなったことがある方は、五十肩になったと思われることが多いかもしれません。しかし、「五十肩」という病名はありません。
五十肩という言葉は、1797年に発行された俚諺集覧(りげんしゅうらん)(太田全斎著、江戸時代)という書物の中に、「凡、人五十歳ばかりの時、手腕、骨節の痛むことあり、程すぐれば薬せずして癒ゆるものなり、俗にこれを五十腕とも五十肩ともいう。 又、長命病という」と記載があります。長寿の病気であり、薬を使わず治癒すると書いてあります。
五十肩・肩関節周囲炎は肩に炎症が起きている状態を表す言葉です。その原因を明らかにすることにより患者さんに応じた治療を提案していくことになります。
原因
肩関節を構成する筋肉、腱、関節包、滑液包、骨などは年齢とともに損傷し、炎症を起こし痛みを発生させます。関節包や滑液包の炎症、腱板断裂、変形性肩関節症、石灰沈着性腱板炎などが原因として考えられます。
また、関節包や滑液包などの組織が炎症により癒着すると肩関節の動きが悪くなります。そのような状態になると肩関節拘縮、凍結肩などと呼ばれ可動域が著しく悪化し日常生活に支障をきたします。
どんな症状?
- 運動時に疼痛があり、動かすのがつらくなります。
- 夜間に痛みがでて眠れないこともあります。
診断
肩の痛み部位や性状を触診します。肩関節が炎症を起こしている原因を探るためにレントゲン、超音波検査、MRIを行います。
※当院にはMRI機器は設置されておりません。
治療
投薬
鎮痛剤を用いて痛みを抑えます。炎症を抑える効果もあります。
注射
除痛や炎症を抑えるため注射を行います。
1. ヒアルロン酸注射
炎症を抑え、潤滑油のような役割があり癒着を防止します。
2. ステロイド注射
ステロイドは炎症を抑える強い作用があります。炎症抑えることにより痛みを軽減します。副作用があるため頻回には注射できません。
3. キシロカイン注射
即効性があり、痛みを軽減しますが長続きはしません。ヒアルロン酸やステロイドに混ぜて使用することが多いです。
リハビリ
肩関節周囲炎の治療の基本となるかもしれません。理学療法士中心にすすめていきます。痛みの強い時期をすぎたら拘縮予防や血流改善のため電気治療や温熱療法を行います。拘縮を起こしている場合は運動療法を行います。
マニピュレーション
肩関節が癒着して動きが悪くなっている場合に行います。ブロック麻酔下に痛みがなるべくない状態にして、医師の手により関節包を破るように関節を動かします。当院では取り扱っていませんので専門医のいる病院への紹介となります。
五十肩の原因となる腱板断裂について
腱板断裂の有病率は高く、ある自治体の健康診断で全体の22.1%の方に腱板断裂があったと報告されています。年齢があがるにつれ有病率はあがります。「五十肩」と診断された方では実は1/3の方が腱板断裂であったともいわれています。
腱板断裂って何?
腱板は肩甲骨と上腕骨をつないでいる筋肉です。肩関節の運動や安定のために大事な筋肉です。スポーツや怪我での損傷や、加齢により徐々に切れてくることをいいます。
どんな症状?
- 特徴的な症状は夜間痛
夜ズキズキして眠れない
痛みで目が覚める - 動作時の痛み
肩を横に上げると痛い、途中で力が入らなくなる。 - 力の低下
ペットボトルの蓋が開けられない
肩関節痛の症状は似たようにものが多いですが、動く範囲はしっかりしているのに動かす途中で痛みがでる、引っかかり感があると腱板断裂の可能性が高いです。
診断
- 問診、診察、画像検査を行います。
- レントゲン、超音波検査、MRIなどを行います。
※当院にはMRI機器は設置されておりません。
腱板断裂の治療
1. 保存療法
鎮痛剤の内服や外用、注射で痛みをとります。
痛みがとれてきたらリハビリを行います。時間が経過してくると肩関節が固くなってくることがあります(凍結肩)。そんな方には肩甲骨の動き促すことや肩関節の可動域を回復させます。
腱板断裂において、保存療法(リハビリ)を行った場合と手術を行った場合、1年後において痛みの改善度に大きな差はないとの報告もあります。このため、初期治療として保存療法を試み、改善が見られない場合に手術を検討するアプローチが一般的です。
保存療法で約7割のかたは症状が軽快するとされています。
2. 手術療法
保存療法で回復してこない場合は手術を考慮します。スポーツ復帰される方や力仕事で筋力を必要とされる方には積極的に考慮します。
1~2ヶ月の装具固定と3ヶ月~半年のリハビリ加療が必要です。
手術が必要と判断した場合は専門医を紹介させていただきます。